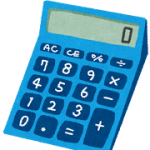 皆さんは、自分が死んだら相続税がかかり、妻、子ども、孫が相続する財産が減るとなったら、生きているうちに財産の一部を贈与してしまおうと考えるでしょう。そこで、国は相続税の減少を防ぐために贈与に対して贈与税をかけています。贈与税は相続税を補う税金だといえます。
皆さんは、自分が死んだら相続税がかかり、妻、子ども、孫が相続する財産が減るとなったら、生きているうちに財産の一部を贈与してしまおうと考えるでしょう。そこで、国は相続税の減少を防ぐために贈与に対して贈与税をかけています。贈与税は相続税を補う税金だといえます。
贈与税の計算方法
亡くなった方が財産を持っていると、相続税がかかります。一方、贈与税は、1月1日から12月31日までの間に受けた贈与に対して、贈与を受けた人が、翌年3月15日までに贈与税の申告と納税をしなければなりません。
1年間に受けた贈与の合計から110万円を引いた残りに贈与税がかかります。ですから、贈与された金額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。110万円を超えた場合には、以下の算式で贈与税を計算します。
A(課税贈与金額)=贈与財産の合計金額ー110万円
| A | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | なし |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
※平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後に父母や祖父母から贈与を受けた場合には、贈与税の税率が現行より引き下げられることになりました(減税)。
例1 400万円贈与してもらった場合
400万円ー110万円=290万円・・・A
Aが300万円以下なので、
290万円×15%ー10万円=33万5,000円
例2 800万円贈与してもらった場合
800万円ー110万円=690万円・・・A
Aが1,000万円以下なので、
690万円×40%ー125万円=151万円
例1と例2を比較してみると、贈与した金額は2倍になっていますが、贈与税は約4.5倍となり、117万円増加しています。贈与税の税率は相続税以上の税率となっているのです。また、このように金額が増える割合以上に税金が増える税制を、累進課税といいます。
贈与税の問題点と相続時精算課税制度について
贈与税が相続税の減少を防ぐ税金だといっても、相続税は全員にかかるわけではなく、毎年亡くなった方の1割以下の方しか相続税の対象になっていません。しかし、相続税を納めるほどの財産をもっていなくても、贈与をすれば贈与税がかかってきます。
もしも贈与税がなければ、衣食足りてそれほど消費しない高齢世代から、住宅、育児、教育、等で消費活動の盛んな次世代に資金が移動し、消費が拡大して景気がよくなることが考えられます。
そこで、平成15年から相続時精算課税制度ができました。相続時精算課税制度とは、通常の贈与税とは別の贈与税の計算方法のことで、税務署に届けを出してこの制度を選択すると、贈与税の税金を相続税納付のときに控除できるものです。もしも相続税がゼロであれば、贈与されたときの税金が全額戻ってきます。いずれの方法が有利かは、人によって異なります。詳細は税理士にご相談ください。
なお、平成25年度の税制改正により、相続時精算課税制度の見直しが行われました。平成27年1月1日以後の贈与より、受贈者の範囲に20歳以上の孫(現行:20歳以上の推定相続人のみ)が追加され、贈与者の年齢要件が60歳以上(現行:65歳以上)に引き下げられました。
