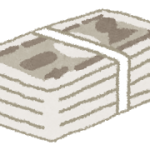 高齢化社会の進展とともに、死後に支払われる保険だけではなく、生きていたら支払われる保険にも関心が集まっています。年金に関する税金はあまりなじみのないものです。うっかり贈与税がかかってしまわないように気をつけましょう。
高齢化社会の進展とともに、死後に支払われる保険だけではなく、生きていたら支払われる保険にも関心が集まっています。年金に関する税金はあまりなじみのないものです。うっかり贈与税がかかってしまわないように気をつけましょう。
生命保険料控除
保険料の支払時に生命保険料控除が利用できます。ただし、それほどの額ではないので、年金に入ろうか、いくらにしようかと考えるときは生命保険料控除を考慮しないほうがよいでしょう。
年金と税金
年金は受け取るときに毎年、雑所得として課税されます。年金の額からこれに対応する払込保険料を控除した額が雑所得となります。公的年金と異なり、公的年金控除(所得控除)がありません。このほか、贈与税や相続税がかかることもあります。ただし、相続税法の規定により、相続税や贈与税がかかった部分については所得税はかかりません。この場合には、支給される年金の額のうち所得税がかかる部分の額から、その額に対応する払込保険料を控除した額が雑所得となります。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎年 | そのほか | ||||
| 満期 | A(夫) | 関係なし | A(夫) | (注1) | ー |
| B(妻) | (注2) | 贈与税 | |||
| 死亡 | A(夫) | B(妻) | (注2) | 相続税 | |
| B(妻) | A(夫) | (注1) | ー | ||
| C(子) | (注2) | 贈与税 | |||
(注1)所得税や住民税がかかります
(注2)相続税・贈与税がかかっていない部分に所得税や住民税がかかります
年金と評価
年金を受ける権利は財産の一種とされ、相続税や贈与税の対象になります。相続税と贈与税は、財産の評価額によって金額が異なります。
年金を受ける権利の評価額は、年金の種類、支給開始の前後いずれかによって異なります。
以下の図の①から⑤まで、評価額の計算方法が異なります。具体的な計算については、税理士または税務署にお問い合わせください。
| 年金の種類 | 年金受給内容(期限) | 生 | 死 | 評価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期限内 | 期限後 | 期限内 | 期限後 | 支給開始 | |||
| 前 | 後 | ||||||
| 終身 | 生きている限り出る | ○ | ○ | × | × | ① | ② |
| 保険期間付終身 | 生きている限り出る なおかつ、あるときまでは死んでも出る |
○ | ○ | ○ | × | ③ | |
| 確定 | 生死にかかわらず、あるときまでは出る | ○ | × | ○ | × | ④ | |
| 有期 | 生きていれば、あるときまで出る | ○ | × | × | × | ⑤ | |
個人年金の税務上の取り扱いの変更
○相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取り扱い
平成22年7月6日の最高裁判所の判決により所得税法が改正され、同年10月20日に施行されました。これまでは、個人年金については、相続等により取得したものであるか否かを問わず、その支払いを受ける年金の所得金額の全額に所得税がかかっていました。しかし、この改正により、相続税や贈与税がかかった部分については所得税がかからないこととなりました。
この変更により、所得税については平成22年分から変更後の計算方法に基づいて計算が行われています。また、平成20年分以後の年分において税金を納め過ぎになっている人については、一定の手続きを行うことにより、税金の還付を受けられる(=税金を返してもらえる)ことがあります。
<取り扱いの変更の対象となる人>
次の(1)~(3)のいずれかに該当する人で、保険契約等に係る保険料の負担者でない人です。
(1)死亡保険金を年金形式で受給している人
(2)学資保険の保険契約者が亡くなったことに伴い、養育年金を受給している人
(3)個人年金保険契約に基づく年金を受給している人
※実際に相続税や贈与税などの税金を払わなかった人も、この変更の対象となります。
○平成20年分以後の年分において税金を納め過ぎになっている人は
一定の手続きを行うことにより、税金の還付を受けられることがあります。
<手続きの場所>
(1)所得税の還付を受けるとき・・・税務署
(2)所得税は還付とならないが、住民税や国民健康保険税などが減額となるとき・・・市区町村
<手続きの期限>(所得税の還付を受けるとき)
(1)既に確定申告をしている年分の手続き(更生の請求)
この取り扱いの変更を納税者の人が実際に知った日の翌日から2ヶ月以内に手続を行う必要があります。また、更生の請求に基づき払い過ぎの税金を返してもらえる期間は、原則としてその申告書を提出した日から5年間となりますのでご注意ください。
(2)確定申告をしていない年分の手続き(確定申告または還付申告)
これから申告する年分の翌年1月1日から5年を経過する日までに行う必要があります。
<注意点>
(1)還付を受けることができるかどうか、また、その還付金の額は、各人によって異なります。
(2)還付の可能性がある人に対しては保険会社等から通知書が送られていますが、通知書が届かない場合も取り扱いの変更の対象となるのではないと思われる人は、保険会社等に確認してください。
(3)具体的な手続きの方法は、税務署等にお問い合わせの上、期限内に手続きを行ってください。国税庁のホームページに詳細な説明がのっています。
(4)住民税については、お住まいの市区役所にお問い合わせください。
○平成22年10月20日以降に、対象となる個人年金を初めて受け取ることになった人は
個人年金の種類に応じ、その年金の残存期間年数・支払総額等をもとに所得税の金額を計算します。具体的な計算については税理士または税務署にお問い合わせください。

年金の課税方法は?
年金は受け取るときに毎年、雑所得として課税されます(一定の個人年金については、雑所得として課税されない部分もあります。)。公的年金も雑所得になりますので、確定申告では個人年金と公的年金を合計して雑所得を計算します。
